20060616
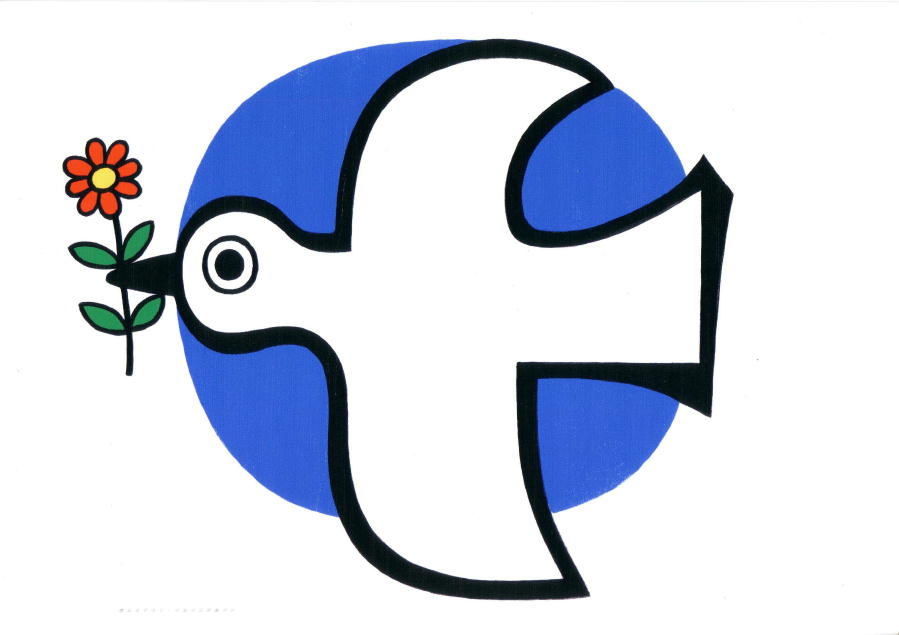
憲法を守ろう・市原市民連絡会
学習シンポジウム
中国から見た日本
来日の中国人、留学生、残留孤児帰国者に聞く
2006年6月16日(金) 18:30〜20::30
市原市民会館大会議室
■ シンポジウム報告
● 開催までの経緯
サッカー・アジアカップの際中国で吹き出した日本批判行動をきっかけに、日本では中国を批判する報道が目立つようになった。日本国首相の靖国神社参拝に中国が反発して首脳会談が行われない状態が続き、海底ガス田開発問題があり、いまでは「戦争やむなし」と言いかねないような「識者」も登場している。
そういうときだからこそ、中国人の生の声を聞きたいと考えた。自称「定年オジサン」、市内で日本語教室を開き外国人と交流の多いSさんに相談すると、趣旨に理解を示し、人選を引き受けてくださった。
日本に滞在しているのに日本を批判することにもなる。中国独特の言論事情もある。そういう中で、靖国問題、憲法問題など政治問題での発言をいとわない方々を集めくださった。すなわち、30歳前後の大学院留学生、50歳前後のビジネスマン、70代の残留孤児永住帰国者である。立場も年齢層もバラエティに富んでおり、さまざまな角度から「中国人の日本観」を聞くことのできる陣容が整った。あとは司会者の技量である。
しかし、ビジネスマンが辞退され、ビジネスウーマンに変更したのだが、その方も当日の時間外労働を余儀なくされ、参加できなくなってしまった。その代役として、残留孤児である奥さんとともに来日され、日本国籍を取得された方が参加された。
定刻より5分遅れて開会。
司会者Sさんから開会のあいさつ。
憲法を守ろう・市原市民連絡会共同代表のMさんのあいさつ。

<三十数名と聴衆が少なかったのはザンネン>
ここからシンポジウムが始まる。
まずシンポの司会者が当日配付資料を使って、昭和戦前期における日本の中国侵略の概要を説明する。関東軍の名前の由来やその守備範囲は、初めて知る人が多かったようだ。
● 残留孤児の訴えと裁判への支援要請 残留孤児永住帰国者Aさん
残留孤児体験を、文化大革命当時の苦況を、国家賠償を求める訴訟への支援の訴えを熱く、日中友好の必要性を切々と語られた。その立場からすれば、首相の靖国参拝には賛成できないし、日中不戦の誓いを実行するには平和憲法は格好の拠り所になる。九条の会の活動も視野に入れておられた。
最後に「日本政府のわれわれへの仕打ちを考えると怒りがこみ上げてくる。感情をあらわにして申し訳ない」と述べられた。
みなさんは、日本国家に三度棄てられたという。一度めは満州移住。貧しい農民を開拓民として送りだしたことである。二度めはソ連侵攻の時点。ソ連の進行が予想される中、関東軍は満州の大半を放棄し、大連・新京間の満鉄線の東側(朝鮮寄り)のみを防衛する作戦を立て、主力部隊を撤退させており、奥地には約20万人の開拓民だけが置き去りにされた。開拓民の中に青壮年はほとんどいなかった。関東軍に「根こそぎ動員」されていたからだ。年寄り、女・子どもだけでソ連軍の前に放り出されたことである。三度めは、永住帰国しても、定住促進センターで半年間の日本語教育を受けただけで、あとは自活を強いられる。そのために多くが生活保護を受けざるを得ない。養父母訪問・墓参に中国に訪ねると、生活保護を打ち切られてしまうなどの理不尽な扱いを受けていることである。
くわえて1959年3月3日には「未帰還者に関する特別措置法」が公布され、当時戦時死亡確認がなされていなかった3万3千人に、「戦時死亡宣告」がなされ、およそ1万3600余名の戸籍が抹消されている。日本と連絡の取れなかった多くの残留婦人・残留孤児の戸籍も抹消された。このため、戸籍の復活には多くの手間と日時が必要だったという。
これらのことについて謝罪・補償し、これからの生活に対して特別措置を講じてほしいとして、全国で訴訟を起こしている。訴訟の提起にあたっても、生活保護の打ち切りをちらつかせた妨害工作があったという。最初の大阪地裁では敗訴。東京地裁は結審し、07年1月に判決。神戸地裁では7月に結審を迎える。
支援団体事務局のTさん
支援要請と署名要請があり、フロアの参加者がただちに応じた。
ちなみに、残留孤児とは1945年8月9日時点で13歳未満の者をいう。残留婦人・邦人とは同13歳以上の者をいう。残留孤児の数は、定住促進センターのサイトによれば、総数2800名、永住帰国者2503名、残留者296名(ママ)となっている。
Mさん
奥さんが孤児永住帰国者であり、いまは中華料理店を営んでいる。最初は日本語で話していたが、苦しくなってきたので、Aさんに通訳していただいた。
「85年に来日したとき、日本の第一印象はとてもよかった。街もきれいだし、人も親切だった。日本国籍も取得したが、しかし最近は少し違ってきた。日中友好を阻害している靖国参拝には強い憤りをもっている」そうな。進行の都合を考えて、発言時間を調整してくださった。
● 留学生の日本観 Lさん
(1) 日本・日本人の印象
内陸部で暮らしてきたので、外国のことはあまり知らなかった。日本についてもテレビを通じての知識しかなかった。
留学手続をしに北京に行き、そこではじめて、日本大使館員などの日本人に接した。
どこにでも「良い人」「悪い人」はいるものだ。留学生の立場だと、普段接する日本人は支援者が中心である。偏見や先入観をもたずに接している。
(2) 日本軍による被害
出身地は内陸部なので、日本軍の侵攻はなかったと理解していたが、配付資料を見ると占領地域に含まれている。[身内に被害者がいるかどうかには言及されなかった。]
(3) 日本首相の靖国参拝
来日前は政治には疎かった。でも来日してからは、関心をもたざるを得なかった。小泉首相の靖国参拝にはそれなりの「政治的背景」があると思う。[中国と比べれば、日本は情報があふれかえっているであろう。その中で嫌中的報道などを眼にすれば、、その記事を読まざるを得ないだろう。それらの記事をどう受けとめているか、「政治的背景」という言葉にどんな意味をこめているかを詳しく聞く機会がなかったのが、ザンネンだ。]
(4) 平和憲法への評価
中国へ戻ると、家族も隣人も「どんな待遇を受けているか」と心配気に聞いてくる。[日本への偏見から来ているのだろう。だからこそ、個人レベルでの]友好関係が必要だと思う。それを国同士の関係へと広げてゆけば、この世の中から戦争をなくすことはむずかしいかも知れないが、やがてはなくすことができるようになると思う。
* フロアからの質問で、「あなたはいわゆる反日教育を受けているはずなのに、述べられたことはとてもバランスがとれている。それはどうしてか?」と問われた。
最初に述べられた「偏見や先入観をもたずに」[日本人と]付き合った結果であると答えた。
[本人の資質にもよると思うが、生活実感のない観念教育(刷り込み)は、生活実感にはかなわないということなのだろう。]
日本人と結婚して来日したSさんは、フロアで聞いていたが、ご自身の体験を語った。
「わたしは日本に来てこれまでに二度、涙を流しました。一度めはラーメン屋さんでです。わたしが中国人だとわかると、女将さんがわたしに深々と頭を下げて、『日本人は戦争中、中国人にひどいことをいっぱいしました。ごめんなさい』と言ったときです。もうひとつは『火垂るの墓』という映画をみたときです。
戦争になれば、犠牲になるのは年寄りや女・子どもです。戦争は絶対にいけません。だから日本は憲法を変えてはいけません。わたしたち一人ひとりが仲良くなって行けば、国と国との戦争を防ぐことができるでしょう。」
もう、これ以上ない盛り上がりで、ここでお開きにしたかったくらいだ。
このシンポジウムのねらいが達成できたかどうかについては疑問もあるが、日中友好と戦争のない世界を実現するために平和憲法は必要だという点が確認でき、なおかつパネラーの人となりがフロアに伝わったということで、シンポは上手く行ったということにしておこう。
パネラーのみなさん、定年のSさん、そして事務局のみなさん、ありがとうございました。
散会後、近くのファミレスで食事会。わたしのテーブルは残留孤児問題が話題の中心。訴訟代理人の弁護士たちの献身的活動を知る。
次回8月は、同じ敗戦国であるドイツと日本との比較。水島朝穂教授に、戦争責任の追及や戦後補償の負い方、憲法改正などを例に話してもらう。
そのつぎは、アメリカ人の話を聞くというのはどうか? 市原市はアメリカに姉妹都市があるし、ALTもいるぞ!!
● 残留孤児関連サイト
中国「残留日本人孤児」の人間回復の闘いに支えを
http://www.jdla.jp/cgi-bin04/column/zan/diary.cgi
中国帰国者定住促進センター
http://www.kikokusha-center.or.jp/